介護タクシー事業の法律上の根拠:位置づけ
介護タクシー事業は、平成13年と比較的新しくできた制度です。
では、介護タクシー事業の法律上の根拠とその位置づけはどこにあるのでしょうか?
介護タクシー事業の法律上の根拠とその位置づけを理解しておくことは、法令試験対策としても重要です。
自動車六法で、道路運送法の条文を見ますと、1.旅客自動車運送事業、2.自家用自動車による有償運送と3.自家輸送の3つに大きく分類されます。
1.旅客自動車運送事業には、次の種類がありです。
<一般旅客自動車運送事業>①一般乗合旅客自動車運送事業(法4条・許可)(乗合バス)
②一般貸切旅客自動車運送事業(法4条・許可)(貸切バス)
③一般乗用旅客自動車運送事業(法4条・許可)(タクシー)
一般乗用旅客自動車運送事業には、次のア、イ、ウの3種類の事業があります。
ア 法人タクシー事業
イ 個人タクシー事業(1人1車制)事業
ウ 福祉輸送限定(いわゆる介護タクシー)
<特定旅客自動車運送事業(法43条・許可)>
2.自家用自動車による有償運送(一種免許で可能)
NPO法人等による福祉、過疎地有償運送(法79条・登録)
3.自家輸送 無規制(一種免許で可)
学校や病院等の送迎輸送等、他人の需要に応じる輸送でないもの
ここまで来ると、介護タクシー事業の根拠と位置づけが分かって頂けたかと思います。
介護タクシー事業は、道路運送法第4条の法律上の根拠があり、一般乗用旅客自動車運送事業に位置づけられています。前述の1③ウが該当箇所です。
介護タクシー事業の法律上の根拠と位置づけを抑えることは、法令試験対策としても重要です。
というのは、自動車六法には、介護タクシー事業だけでなく、その他の事業も条文が記載されています。介護タクシー事業の法律上の根拠と位置づけをよく理解ていないと、出そうもないその他の一般乗合旅客自動車運送事業などの条文まで手をひろげ、時間を無駄にしてしまいます。
訪問介護員等の自家用有償運送事業
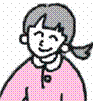
訪問介護員等の自家用有償運送事業があると聞いたのですが、法律上の根拠とその位置づけはどこでしょうか?

結論から申し上げますと、道路運送法第78条3号に法律上の根拠があります。
位置づけとして、前述の2.自家用自動車による有償運送にあたります。
ただし、この訪問介護員等の自家用有償運送事業は、その事業だけを行うことを目的として、単独で申請できません。
つまり、介護保険法の訪問介護または障害総合支援法の居宅介護の指定を受けており、かつ、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー含む)または特定旅客自動車運送事業の許可を受けていることが大条件となります。
路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー含む)または特定旅客自動車運送事業の許可を得ていることが条件であることから、訪問介護員等の自家用有償運送事業のことを「ぶら下がり許可」とも呼ばれています。






